| モデル | 目次 | 赤道暖水域応答実験 |
始めに標準実験(A0)において得られた大気の構造を描写する. この実験を基に後の実験と比較を行なう.
降水量は赤道で最大値を持ち, 南緯および北緯 20 度に極小値をもち, 南緯および北緯 45 度付近に再び極大値をもちさらに北へ進むにつれて 単調に減少する分布となっている(図 3 a).
熱帯域にはスケールが数 1000 km 程度の降雨の激しい領域が形成さ れているのだが, 降水量の水平分布はほぼ東西平均値を東西に並べた分布をしている.
蒸発量は南緯および北緯 20 度に極大値をもち両ピーク値から赤道方向と 極方向へ向かうにつれて減少している.
蒸発量の水平分布は南北に 10 度から 30 度の領域にスケールが 数 1000 km 程度の蒸発の激しい領域が形成されているが, この スケールは降水量において見られたものよりも大きい. 蒸発量の 水平分布は降水量よりも東西に変動の少ない分布をしている.
蒸発量と降水量がちょうどつり合う緯度は南北に 40 度のと 10 度とにおいてである. 赤道から極に向かう 10 度から 40 度の領域 では蒸発量が降水量を上回っている.
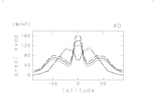 (a)
(a)
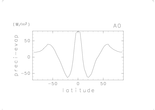 (b)
(b)
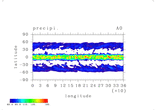 (c)
(c)
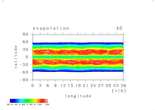 (d)
(d)
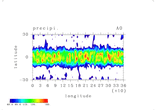 (e)
(e)
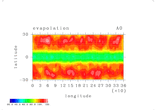 (f)
(f)
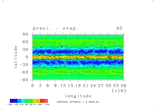 (g)
(g)
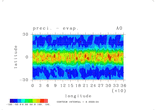 (h)
(h)
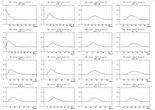 (a)
(a)
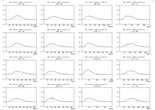 (b)
(b)
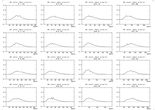 (c)
(c)
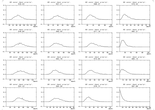 (d)
(d)
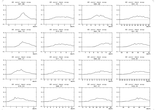 (e)
(e)
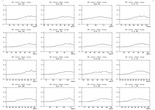 (f)
(f)
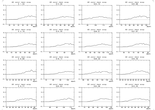 (g)
(g)
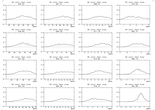 (h)
(h)
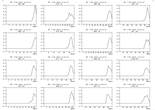 (a)
(a)
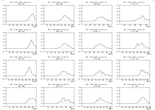 (b)
(b)
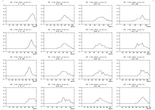 (c)
(c)
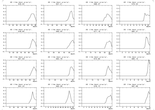 (d)
(d)
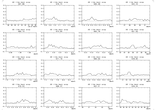 (e)
(e)
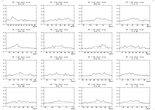 (f)
(f)
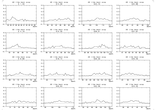 (g)
(g)
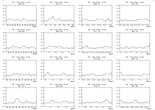 (h)
(h)
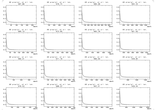 (a)
(a)
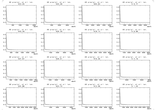 (b)
(b)
 (c)
(c)
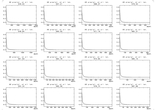 (d)
(d)
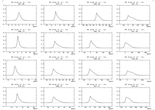 (e)
(e)
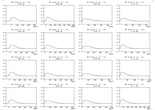 (f)
(f)
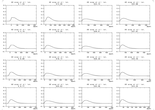 (g)
(g)
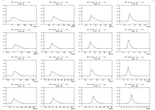 (h)
(h)
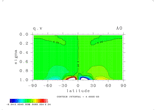 (a)
(a)
 (b)
(b)
 (c)
(c)
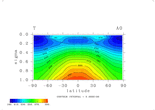 (a)
(a)
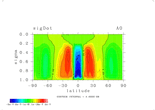 (b)
(b)
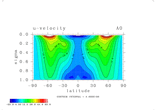 (c)
(c)
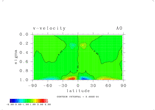 (d)
(d)
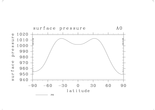 (e)
(e)
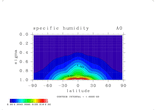 (f)
(f)
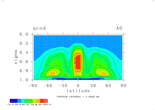 (g)
(g)
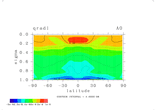 (h)
(h)
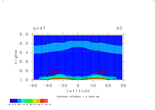 (i)
(i)
 (j)
(j)
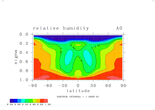 (k)
(k)
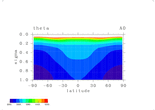 (l)
(l)
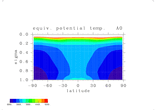 (m)
(m)